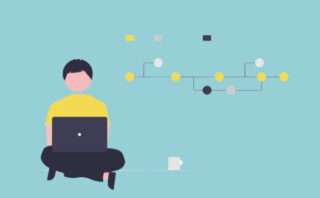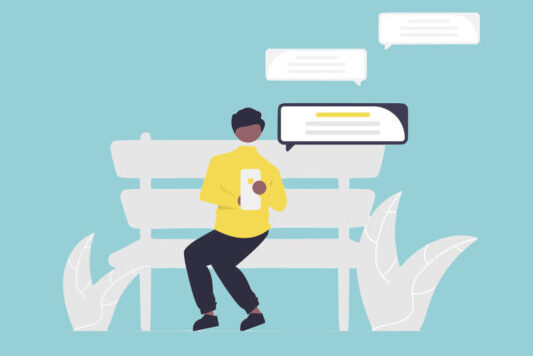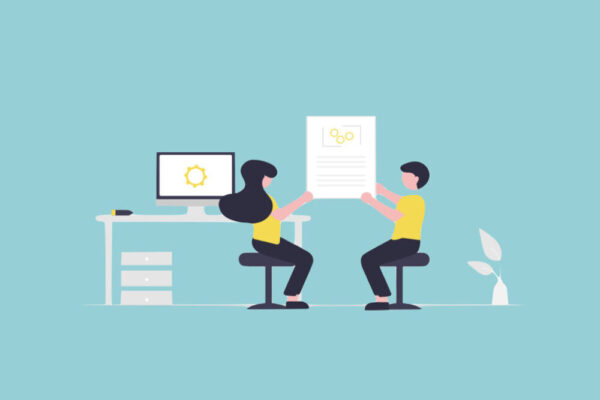今回は、投資の中でも最も代表的な銘柄である「S&P500」への投資について、どのような方法があるのか、またどの方法が最も低コストなのかを、今回徹底的に検討していきたいと思います。
【初心者の方向け】S&P500指数とは?
S&P500は、一度に米国の有名企業に分散投資ができ、一時的に急落しても10年20年の長期で見ると、成長率も安定して高いため、iDeCoやNISA制度を利用しての投資としても、人気のある銘柄となっています。
S&P500指数
簡単に言うと、S&P500指数とは米国の大・中企業の株価を集めた指数です。米国市場の時価総額の70%-80%程度を占めており、S&P500に投資することは、米国の有名企業のほとんどに投資することと同じになります。

少し難しい説明だと、S&P500とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスという投資機関が算出しており、時価総額加重平均型の株価指数になります。時価総額は1941年から1943年の時価総額の平均を10として、現在がどの程度なのかを表しています。現在が3900程度なので、80年間で390倍にも成長している指数ということになります
(上の写真がS&P500指数の推移、細かくみたい方は下のチャートを確認してください)
※VOO:米国ETF(バンガード S&P500 ETF)のチャート
(参考)他の指数
他の米国市場の代表的な指数についても簡単に紹介いたします。
| 指数名称 | 銘柄数 | 対象銘柄の特徴 |
| S&P500 | 500 | 大型・中型 米国市場時価総額の70-80% |
| NYダウ | 30 | 各業種の代表銘柄 |
| NASDAQ総合指数 | 3000以上 | ハイテク銘柄全て |
| NASDAQ100 | 100 | ハイテク銘柄の上位100 |
| NASDAQ次世代50 | 50 | ハイテク上位100に期待される次世代銘柄50 |
各指数で特徴がありますが、投資先としてはS&P500が最もバランスが取れた指数と思います。
各指数に連動する投資銘柄もありますので、気になる方は各指数名称にリンクを貼っていますので、記事をご確認ください。
3つの S&P500指数への投資方法
S&P500へ投資できる銘柄は、大きく3つあります。
- 投資信託(日本の証券会社などで購入する)
- 国内ETF(日本の株式同様に購入する)
- 米国ETF(米国市場の株式同様に購入する)
ここではそれぞれの特徴について詳しくは触れませんが、投資信託が最も手間がなく簡単に投資でき、下に行くほど手間がかかるというイメージです。米国ETFでの投資が最も手間がかかります。
また投資信託とETFの違いについて知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
3つの 運用コストについて
3つの投資方法を紹介しました。いよいよ本題のコストです。
それぞれ金融”商品”なので、持つことにコストがかかります。どのようなコストなのか、まとめたのが以下の表になります。
| 投資信託 | 国内ETF | 海外ETF | |
| ①経費率 (信託報酬) | 必要 | 必要 | 必要 |
| ②売買手数料 | S&P500に連動する ものは無料が多い | 無料 | 必要 |
| ③為替手数料 | 不要 | 必要だが①に 含まれることが多い | 必要 |
大きく3つのコストがあります。一見、米国ETFが最もコストがかかりそうな印象です。
【シミュレーション】実際に運用した場合のコストを試算
早速ですが、コストを比較していきます。
3つのそれぞれ比較し、最後にまとめます。読むのが面倒な方は、最後のまとめまで飛ばしても問題ありません。
具体的にコストを計算していくため、以下の実際の銘柄で計算していきます。
シミュレーションする各銘柄
- 投資信託:SBI – SBI・バンガード・S&P500 インデックスファンド
- 国内ETF:2558 MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信
- 米国ETF:VOO バンガード S&P500 ETF
また実際の環境に合わせて計算するため、投資した銘柄は以下の条件で運用されると仮定します
運用条件
100万円投資し、10年後に200万円(10年で2倍)となり、その後全て売却する
※年7%の上昇が続くと、10年後2倍になります。過去20年間の平均が6-7%なので、分かりやすいように7%、10年間で2倍で計算しています。
① 経費率(投資信託報酬)
ここでは経費率を比較します。経費率とは信託報酬とも呼ばれ、銘柄を維持するのに必要な費用とイメージしていただければと思います。
実際の経費率は、毎日のように少しづつ引かれていきますが、ここでは1年後の資産に対し、各経費率分のコストがかかると計算し、毎年のコストを10年間分合計した数値を赤字で記載しています。
|
経費率 |
投資信託 |
国内ETF |
米国ETF |
|
ファンド名 (ティッカーシンボル) |
SBI・バンガード・S&P500 インデックスファンド |
2558 MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 |
VOO バンガード S&P500 ETF |
|
信託報酬 |
0.0938% |
0.0858% |
0.03% |
|
その他 |
+0.1% |
+0.1% |
無し |
|
経費率 合計 |
0.1938% |
0.1858% |
0.03% |
|
10年間の経費率合計(円) |
28651 |
27468 |
4435 |
結果、投資信託が最も高く、米国ETFが最も少ない結果となりました。投資信託と国内ETFは後から出てくる、為替コストなども含まれていることもあり、少し高い結果となっています。
② 売買手数料
売買手数料は、米国ETFのみ必要となります。S&P500以外にもメジャーな指数に連動する投資信託等は、売買手数料が無料の物が多いです。
|
売買手数料 |
投資信託 |
国内ETF |
米国ETF |
|
ファンド名 (ティッカーシンボル) |
SBI・バンガード・S&P500 インデックスファンド |
2558 MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 |
VOO バンガード S&P500 ETF |
|
購入時 |
0円 |
0円 |
0円 |
|
売却時 |
0円 |
0円 |
0.495%(最大22ドル) |
|
100万円購入後、 200万円分売却した場合 ($1=100円と仮定) |
0円 |
0円 |
22ドル |
|
2200円 |
売買手数料は、米国ETFの売却時のみ必要となります。
200万円売却したとして、2,000,000×0.495%=9900円ですが、最大2200円なので2200円でシミュレーションを続けます。
③ 為替コスト
為替手数料ですが、多くの証券会社では$1あたり25銭の手数料が必要となります。
しかしSBI銀行では、買い付け時0.02円/$、売りつけ時0.04円/$とめちゃくちゃ安いです。これが米国株を購入する際、SBI証券が勧められる理由の一つになります。
ここでは投資信託もSBIの最も低コストの商品で比較を進めていますので、上記の安い為替手数料で計算を進めます。
|
為替手数料 |
投資信託 |
国内ETF |
米国ETF |
|
ファンド名 (ティッカーシンボル) |
SBI・バンガード・S&P500 インデックスファンド |
2558 MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 |
VOO バンガード S&P500 ETF |
|
円→ドルの時 |
ー |
ー |
0.02円/$ |
|
ドル→円の時 |
ー |
ー |
0.04円/$ |
|
100万円で10000ドル買うと、 (1ドル=100円と仮定) |
ー |
ー |
200円 |
|
20000ドルを200万円に変えると、($1=100円と仮定) |
ー |
ー |
800円 |
|
為替手数料 合計 |
無し |
無し |
1000円 |
一見、米国ETFのみ為替手数料がかかっているように見えますが、投資信託と国内ETFは経費率(信託報酬)に含まれていることがほとんどなので、実質的にはどの銘柄も為替手数料は発生しています。
コストまとめ
3つのそれぞれのコストを計算したので、最後にまとめて見てみましょう。
|
|
投資信託 |
国内ETF |
米国ETF |
|
ファンド名 |
SBI・バンガード・S&P500 インデックスファンド |
2558 MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 |
VOO バンガード S&P500 ETF |
|
経費率 |
28651 |
27468 |
4435 |
|
売買手数料 |
0 |
0 |
2200 |
|
為替手数料 |
0 |
0 |
1000 |
|
コスト試算合計(円) (10年間合計) |
28651 |
27468 |
7635 |
結果、米国ETFが投資信託・国内ETFに比べ、1/3~1/4程度コストが安いことが分かりました。
但し、為替は住信SBIネット銀行で自分で交換すること、投資していた資金は一度に全て売買することが前提条件になります。
仮に、200万円を少しづつ売却する場合、米国ETFはその都度手数料が必要なので、必要コストは上がっていきます。
要は、米国ETFは自分で色々調べて、手間をかけて投資する分、コストが安いと言うわけです。
逆に、手間をかけたくない人は、投資信託で投資を行うことをオススメします。コストが高いと言っても、2万円程度ですし、為替の色々な手続きや売却のタイミングなど考えなくていいので、正直かなり楽チンです。
(参考)コスト以外に注意する点
流動性について
流動性とは、市場に出回る数の多さによるもので、多くの数が出ていれば流動性は高いということになります。市場に多くの数の商品があると言うことは、自分が取引したい金額で売買ができる可能性が高いと言うことになります。
例えば、流動性が低い商品は、市場で扱っている人々が少ないため、「自分の持っている銘柄を〇〇円で売りたい」となっても、そもそも売買している人が少ないため、思った金額で売れない場合が発生しやすくなります。
この流動性について、各3つの銘柄比較すると、以下になります
|
2021/02/19時点 |
投資信託 |
国内ETF |
米国ETF |
|
ファンド名 |
SBI・バンガード・S&P500 インデックスファンド |
2558 MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 |
VOO バンガード S&P500 ETF |
|
購入最低金額 |
100円~ |
約11800円~ |
約36000円~ |
|
注文方法 |
終値 |
指値・成行 |
指値・成行 |
|
流動性 |
△ |
× |
○ |
投資信託は、売買金額を指定できない・売買されるまで分からないと言う点で「△」にしています。
また国内ETFは、先ほどの表現だと「流動性が低い」ため「×」としています。
この点でも、米国ETFに利点があるといえます。
分配金について
上記の計算の結果、米国ETFが運用コストが安いと分かりましたが、一つ注意点があります。
それは、分配金についてです。これに関しては、別記事で詳しく説明しますが、
例えば100万円投資すると、S&P500に関する商品だと、おおよそ1年間で1.5万円の分配金を得ることができます。(個別株で言う配当みたいなイメージです)
この分配金ですが、投資信託であれば自動的に再投資されます。しかしETFの場合、一度自分の口座に振り込まれるため、複利の力で資産運用したい場合、自分でもう一度ETFを購入しなければなりません。
さらに問題なのが米国ETFの最低購入金額が3万円を超えていることです。分配金を再投資しようとしても、分配金だけでは米国ETFを追加購入できません。つまり2年に一度しか再投資できない状況になります。この間も投資信託は、再投資した分も7%で成長を続けるので、10年間もあれば2万円のコスト差が埋まる可能性があります。
詳細については、以下の記事をご確認ください。
【結論】S&P500への投資時のオススメ銘柄
コストから判断
- 手間をかけてでもコストを抑えたい人 → 米国ETF(バンガード S&P500 ETF (VOO))
- ややこしい手配を避けて楽して投資したい人 → SBI-SBI バンガード S&P500 インデックスファンド
になると思います。皆さまそれぞれで投資方針など異なると思いますので、自分の好みに合わせてお選びになるといいかと思います。
まとめ
この記事では、S&P500指数に投資するための、各銘柄について、運用コストを計算し比較しました。単純なコストだけを比較すると、米国ETFが最も安く、投資信託と国内ETFはぞれほど変わらない結果となりました。
実際に、米国ETF(バンガード S&P500 ETF (VOO))や SBI-SBI バンガード S&P500 インデックスファンドに投資する方法がわからない方向けに、手順と方法を詳しく書いた記事を用意しました。実際に投資を開始してみたい方は、以下の記事をご確認ください。